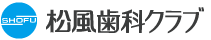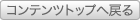MiCD SMILE CIRCLE MEMBER
Interview

貴医院について教えてください
札幌市のベッドタウンである手稲区に院長(父)が開業して34年になります。これまで3回ほど改築をしていますが、3年前に副院長として戻ってきたときにさらに改築し、小さいながらも自分専用の技工室を設けました。松本勝利先生の義歯のセミナーを受講してから、自分で義歯を製作しています。設備については患者さんが最新の治療を受けられるようにオペ室やCT、炭酸ガスレーザ、位相差顕微鏡、う蝕診断用レーザ、オートクレーブとガス滅菌システムなども導入しました。当院では、歯科医師2名、歯科技工士1名、歯科衛生士7名、消毒・滅菌スタッフ2名、受付1名、事務1名の体制で治療にあたっています。
松本勝利先生の「MiCD Hands-on Seminar」に参加されたご感想をお聞かせください
症例による材料の使い分けが最も勉強になりましたね。それまでは材料の使い分けを意識して治療を行うことは多くありませんでしたが、前歯部の審美性を重視する場合にはボンディング層の薄い1ステップボンディング材(ビューティボンド マルチ)を使い、臼歯部の場合には接着強さを重視して2ステップボンディング材(フルオロボンドⅡ)を使うようになりました。今回のMiCDハンズオンセミナーで初めて松風社のフルオロボンド シェイクワンを知りましたが、深い窩洞の症例など歯髄に近接した症例でも使用できる点がよいと思い、採用しました。
また、それぞれの製品の操作ステップを正しくきちんと行うことの大切さに改めて気づかされました。レジンは、重合収縮のコントロールを意識するようになりました。ワンステップボンディング材ではより強固な接着を得るために、擦りつけるように塗布することや、エアブローはしっかりと水分が蒸発するまで行うようになりました。今までないがしろにしがちだった操作とちょっとしたコツを確実に行い、材料の特長が最大限発揮されるように注意しています。
そのほか、咬合面形態の回復方法を学ぶ実習は、咬頭頂の位置をマークしていき解剖学的形態付与の方法を学ぶという、とてもインパクトのある内容でした。色調再現については、シェードテイキングの注意点と築盛量の調整と明度コントロールによる再現方法も参考になりました。
松本先生のセミナーには何度も参加していますが、今回のハンズオンセミナーでも実習の時間を長く取っていただいて、受講生が手を動かして学ぶ時間が十分にあり、満足できる内容でした。MiCDハンズオンセミナー後は、うれしいことに「本当にきれいになった」と驚き混じりに喜んでくださる患者さんの声が増えました。自分でも以前のコンポジットレジン充填修復とは明らかに美しさが違うと感じていますが、まだトレーニングのつもりで行なっており、全て保険診療で行なっています。
松風製品のMiCD製品についてご感想をお聞かせください。
 症例に応じて使い分けている3種類のボンディング材。仮着にはIPテンプセメントを使用されているそうです。
症例に応じて使い分けている3種類のボンディング材。仮着にはIPテンプセメントを使用されているそうです。
 患者さまに見ていただけるよう待合室にMiCD啓発ツールを使用していただいていました。
患者さまに見ていただけるよう待合室にMiCD啓発ツールを使用していただいていました。
S-PRGフィラーが配合されているGiomer製品は炎症が起きにくいと松本先生がお話されていたので、歯肉縁下に窩洞があるケースではビューティフィルシリーズを使用しています。炎症が起きにくいのは、私自身も臨床で実感していますね。残根の症例で隔壁を作って根管治療する時なども、ビューティフィル フロー プラスF00を使っています。
ビューティフィルシリーズは松本先生から教えていただいた一塊充填でも活躍しています。最初はビューティフィル フロー F10で強固な層を作り、ビューティフィルⅡで一塊充填しています。松風社のGiomer製品は使い始めたばかりですが、プラークが付着しにくく予防も期待できるバイオアクティブ機能および製品コンセプトは非常によいですね。
また、研削材ではMiCDダイヤがよいですね。私は10倍のルーペを使用していますが、ネックが細いため視野が妨げられないので、本当に使いやすいと感じています。形態修正はダイヤモンドポイントFG スーパファインを使用し、シリコンワングロスで研磨しています。シリコンワングロスはセミナーを受講してから使うようになりました。コンポマスターやダイレクトダイヤペーストも光沢がよく出るので非常によいですね。
治療において大切にされていることやモットーをお教えください。
天然歯に勝るものはないので「MiCD」に尽きます。患者さんには充填する度に「MiCD」を説明しています。そして、説明の際には、口腔内カメラを使用して3回は治療経過を確認していただいています。1回目は術前、2回目は小さく窩洞形成したところ、3回目はコンポジットレジン充填をした歯を見ていただきます。MiCDハンズオンセミナーに参加してから、確実な充填修復を心がけるようになりました。そして患者さんの歯の延命に寄与しながら、審美性も付与できるという楽しみも出てきました。最近はそれが日々の診療に対するモチベーションにも繋がっています。滅菌においては自分が口に入れてもよいと思えるような器具の消毒・滅菌を心がけるなど、常に“自分が患者さんになった時に受けたい治療”を心がけています。